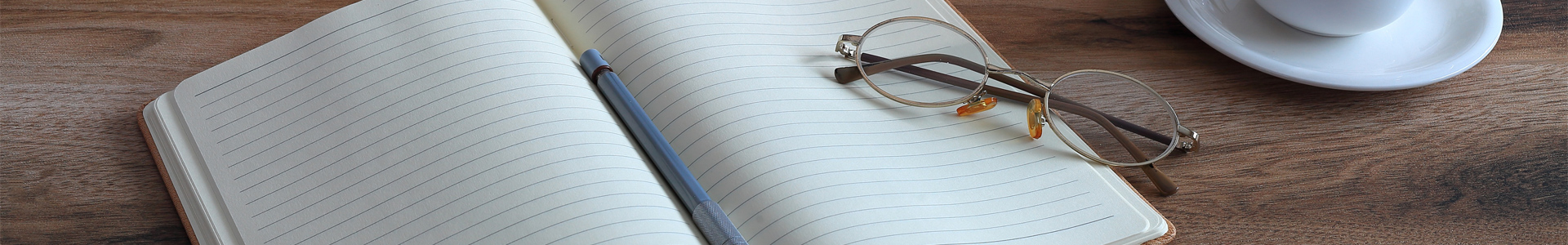⑭寄与分についてはっきりさせたい場合
作成する際は、
「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。
遺言者は、遺言者が有する次の財産を長女の○○和美(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。※財産の表示は省略
付言事項の書き方の例です。
長女の和美は、高校卒業後20年にわたり、家業の青果店を他の従業員の3分の1の給料で手伝い続け、店を大きくすることに貢献してくれました。本当に感謝しています。
前項以外の財産については、子どもたちにそれぞれ法定相続分どおり相続させるので、父の希望を受け入れ、前記財産については、和美の寄与分として認めてほしい。
【解説】
寄与分(きよぶん)とは、相続人の中で 被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人に対して、相続分を増やす制度です。通常の法定相続分とは別に、その貢献度を考慮して多くの財産を受け取れるようにする仕組みです。
寄与分が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①法定相続人であること
例えば、長男や長女、配偶者など、法定相続人に該当する人でなければなりません。長年同居して被相続人を支えていた息子の妻(長男の嫁) などは相続人ではないため、寄与分を主張できません。
②特別な貢献により被相続人の財産が増加もしくは維持されたこと
ただの扶養や介護ではなく、下記のような「特別な」貢献があり、これにより被相続人の財産が増加もしくは維持されたことが必要です。
寄与分の額は 相続人同士の話し合い(協議)で決めるのが原則です。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に寄与分の決定を申し立てることができます。
(詳細は「寄与分」)
従って、遺言書に文例のような記載をしたからといって、そのことから直ちに法的な効力が発生するわけではありません。付言事項となります。