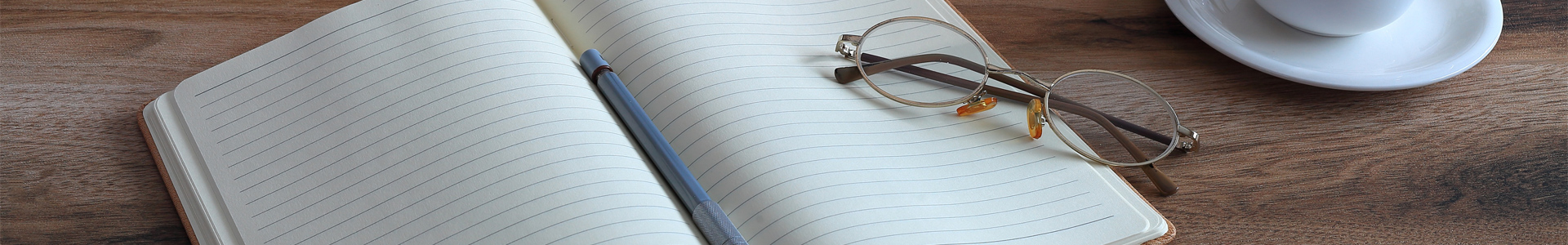⑬生前贈与分を相続財産に加えないようにする場合
作成する際は、
「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。
遺言者が長男の○○一雄(昭和○○年○○月○○日生)の結婚時に住宅資金として援助した1千万円については、特別受益の持ち戻しを免除する。
付言事項の書き方の例です。
長男の一雄には、お母さんの面倒や、先祖の供養などいろいろと経済的な負担をかけることになるので、過去の援助を生前贈与として考慮しないことにしました。
ほかの子どもたちも、お父さんの想いを尊重し、兄弟仲よく、助け合って幸せに暮らしてください。
【解説】
特別受益の持ち戻しとは、相続人のうち、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合、その財産を相続財産に加えて計算し、相続分を決めるという制度のことです(民法903条)。
これは、相続人間の公平を図るための仕組みであり、特定の相続人だけが生前に多くの財産を受け取っていた場合に、他の相続人と不公平にならないようにするためです。
しかしながら、遺言者が「持ち戻ししなくてよい」と明確に意思表示していた場合は、持ち戻しは不要となります(民法903条3項)。文例では、この意思表示を遺言書に記載することによって行っているものです。
しかしながら、特別受益の持ち戻しを免除しても、遺留分の計算においては、免除がないものとして計算が行われます。すなわち、この免除行為によっても遺留分を侵害することはできないという仕組みになっています。
(詳細は「特別受益の持ち戻し」)
特別受益の持ち戻しについて
遺言者からの多大な学費の援助や住宅資金、結婚資金、独立資金の援助などは、相続のときに特別受益として相続分から差し引きます。これが「特別受益の持ち戻し」です。「特別受益の持ち戻し」は遺言によって免除することができます。免除するときは、どのような贈与を免除するのか(上記の例の場合は「結婚時の住宅資金1千万円」)を明記する必要があります。