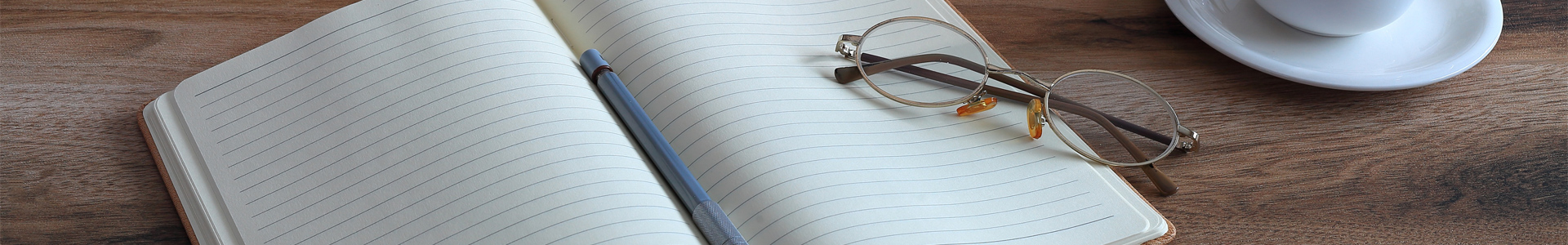⑰過去に作成した遺言書の一部を撤回・訂正する場合
作成する際は、
遺言者は、平成○○年○○月○○日に作成した公正証書遺言の第1項を取り消し、以下のとおり変更する。
「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。
遺言者は、遺言者が有するすべての財産を、遺言者の二男○○次夫の妻裕子(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
付言事項の書き方の例です。
妻が亡くなった後、長年、面倒を見てもらった二男の次夫に全財産を相続させることで報いたいと望んでいましたが、残念なことに私よりも先に次夫が亡くなったため、次夫の妻裕子に全財産を譲ります。
長男の一雄は、父の希望に異議を述べることなく、これからも裕子さんと次夫の子どもたちを助けてあげてください。
【解説】
遺言書は、一定の方式に従えば、生前であればいつでも取り消し(撤回)や変更が可能です。これは、遺言者の意思を最大限尊重するためのルールであり、たとえ過去に作成した遺言があっても、新しい意思が優先されることになっています。
民法1022条(遺言の撤回)は、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる、と規定しています。
「遺言の方式に従って」とありますから、新しい遺言書を作成して取り消す(撤回する)ことになります。新しい遺言を作成すると、前の遺言と抵触する自動的に撤回されたことになります(民法1023条)。なお、法文では「撤回」という言葉が使われていますが、「取り消し」と同じ意味です。
(詳細は「遺言の撤回」)
変更の場合は、前の遺言の記載を取り消し、新しい内容の記載をするということになります。
本文例では、前の遺言の1項を取り消し、新しい内容の記載をすることによって、変更しています。取り消しと新しい内容の記載をすることによって記載内容が複雑になる場合は、全体の記載を書き換えた方がよい場合もあるでしょう。
また、本文例では、前になされた公正証書による遺言を、自筆証書による遺言で変更していますが、この場合でも新しい遺言の内容が優先します。公正証書による遺言がある場合は、公正証書による遺言でなければ取り消しや変更ができないということはありません。