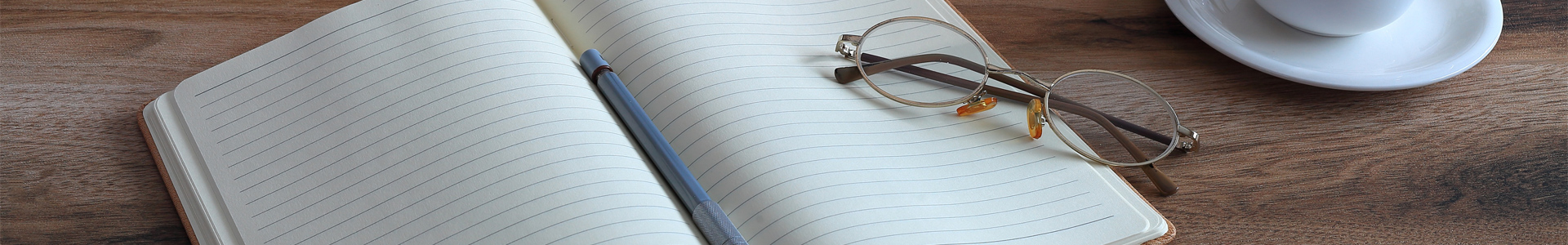④妻が自宅に住み続ける権利(配偶者居住権)を確保する場合
作成する際は、
「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。
遺言者は、遺言者の妻○○花子(昭和○○年○○月○○日生)に、遺言者が所有する次の建物の配偶者居住権を遺贈する。※建物の表示は省略
遺言者は、遺言者の長男○○一雄(昭和○○年○○月○○日生)に、次の建物の負担付所有権を遺贈する。※建物の表示は省略
遺言者は、長男一雄に、次の土地の所有権を相続させる。※土地の表示は省略
付言事項の書き方の例です。
妻花子には、先々の心配をすることなく自宅に住み続けてほしいと考え、配偶者居住権を活用することにしました。
一雄は、お母さんの面倒をちゃんと見てくれると信じていますが、どうか父の想いを受け止めて、お母さんを大切にしてください。
【解説】
本遺言の内容は、建物の所有権は長男に相続させるものの、妻には居住権を与えるものです。
この制度は、民法の改正(2020年4月施行)により新たに創設された権利で、被相続人の配偶者が、住んでいた家に引き続き無償で住み続けることができる権利です。
遺言者は、この配偶者居住権を遺言により設定することができます。
この権利が設定されると、建物の遺贈を受ける長男は負担付きの遺贈を受けることになります。このことを記載したのが、上記文例の2項です。ただ、負担付きで遺贈するとの記載がなくても、1項がある限り、負担付き遺贈になります。
配偶者居住権について
配偶者居住権は、相続開始時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合に、配偶者が無償で住み続けることができる権利で、配偶者の老後の安定した生活を確保させるために創設されたものです。この権利は、遺産分割協議等によって取得することができますが、遺言によることもできます。例えば、相続人が配偶者と被相続人の先妻の子という場合に、居住権のトラブルを回避する手段として有効です。